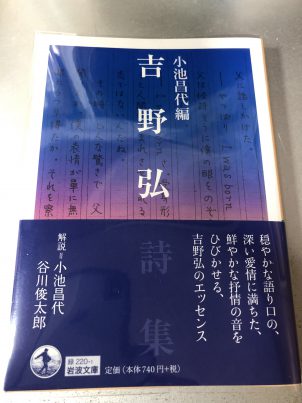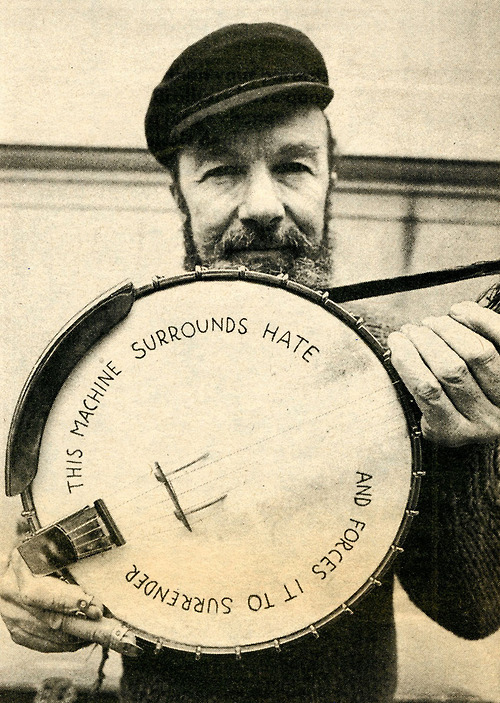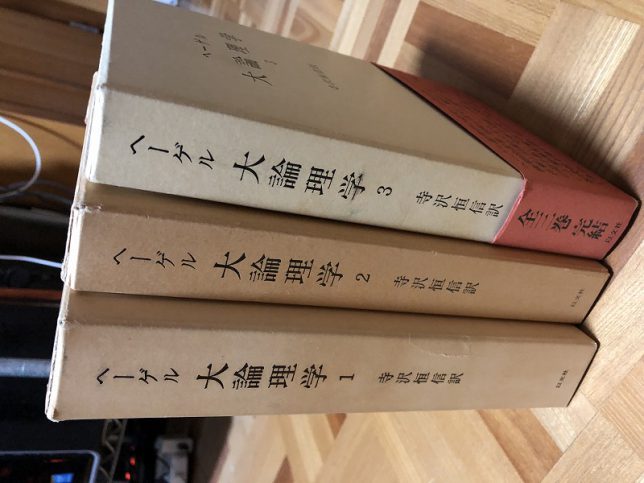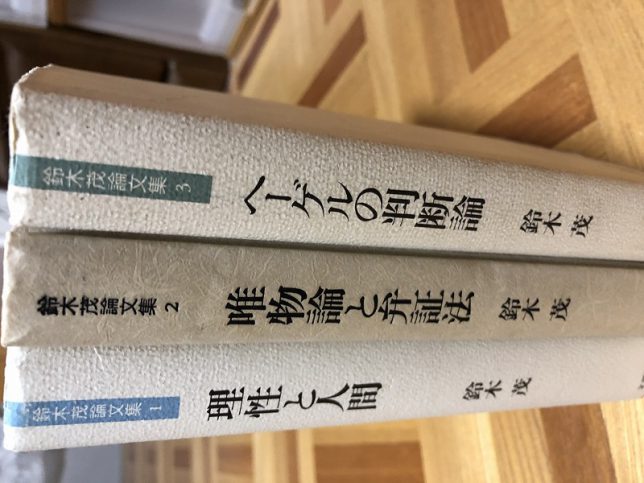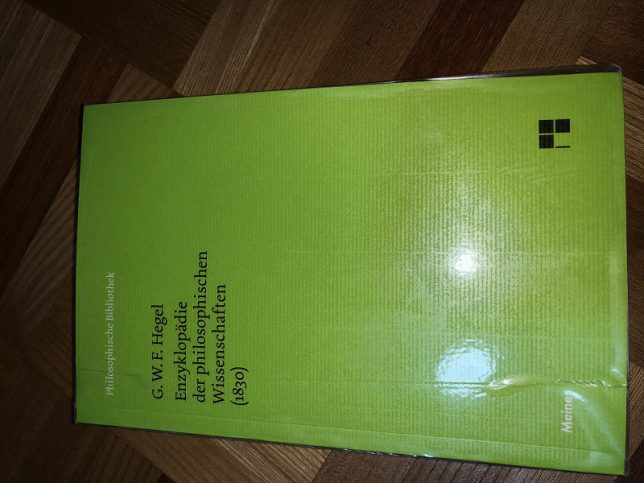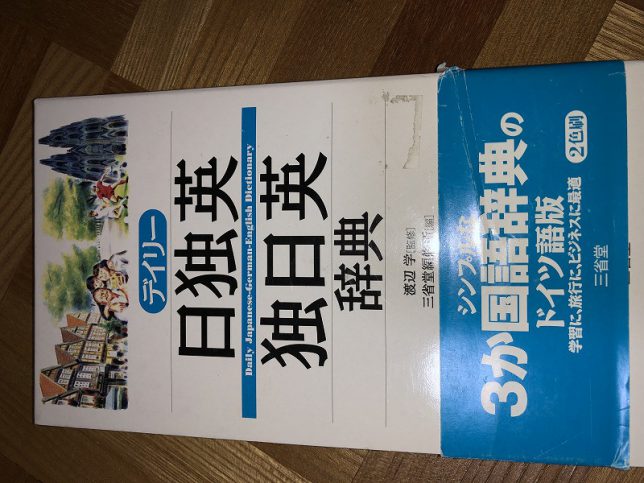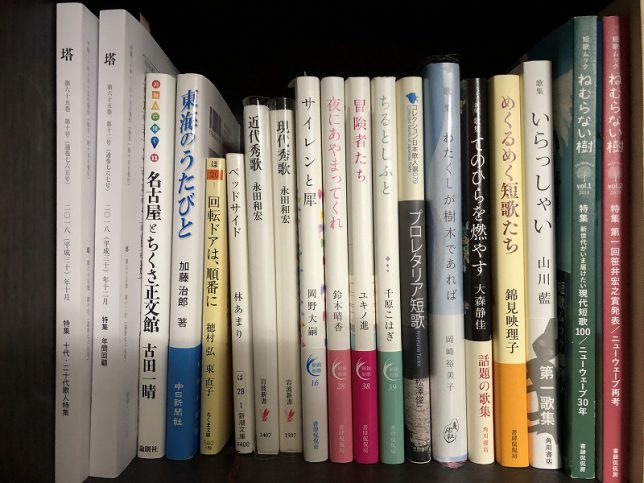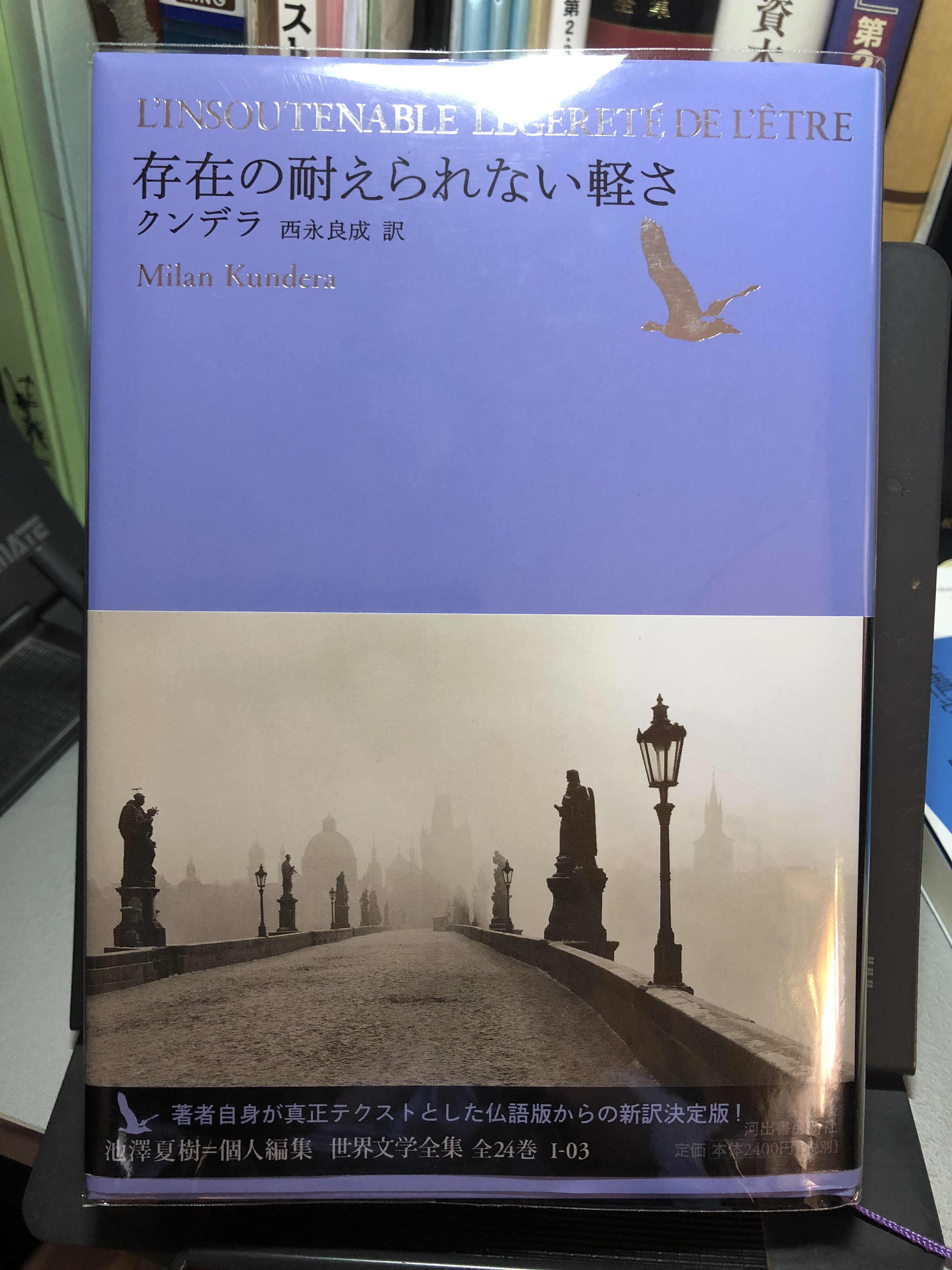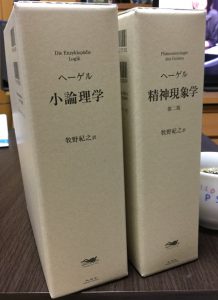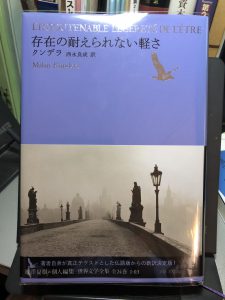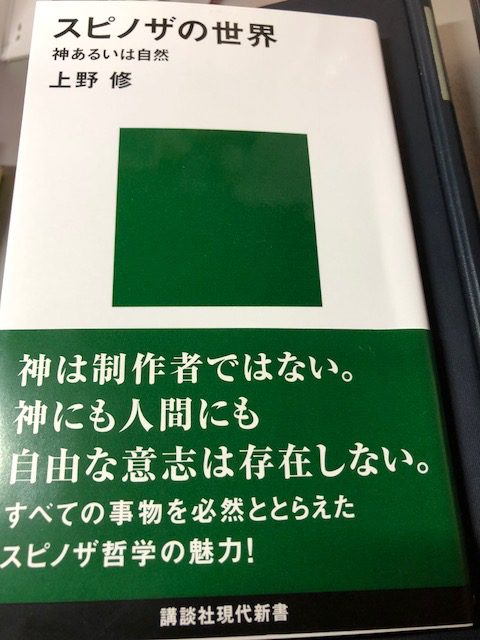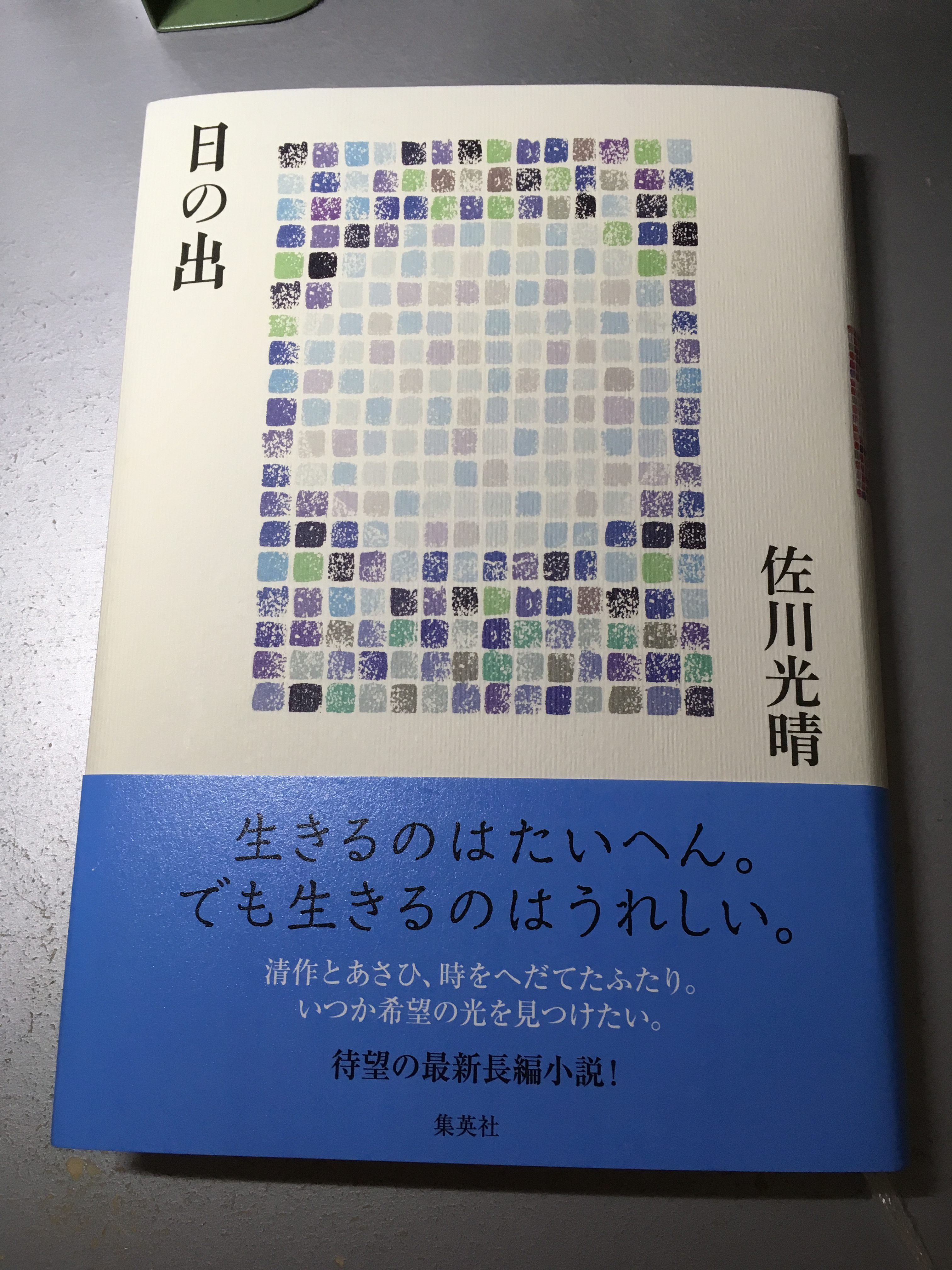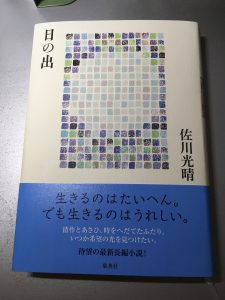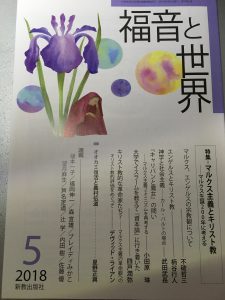歌集 いらっしゃい (まひる野叢書)
新版 歌集 てのひらを燃やす (塔21世紀叢書 第 330篇)
夜にあやまってくれ (新鋭短歌シリーズ28)
しびれる短歌 (ちくまプリマー新書 318)
回転ドアは、順番に (ちくま文庫)
わたくしが樹木であれば
北村太郎詩集 < 現代詩文庫 61 >
唯物論と経験批判論―原典解説 (1966年) (マルクス=レーニン主義入門叢書)
ベッドサイド (新潮文庫)
偶然と必然―弁証法とはなにか (有斐閣選書 (872))
めくるめく短歌たち
サイレンと犀 (新鋭短歌シリーズ16)
近代秀歌 (岩波新書)
現代秀歌 (岩波新書)